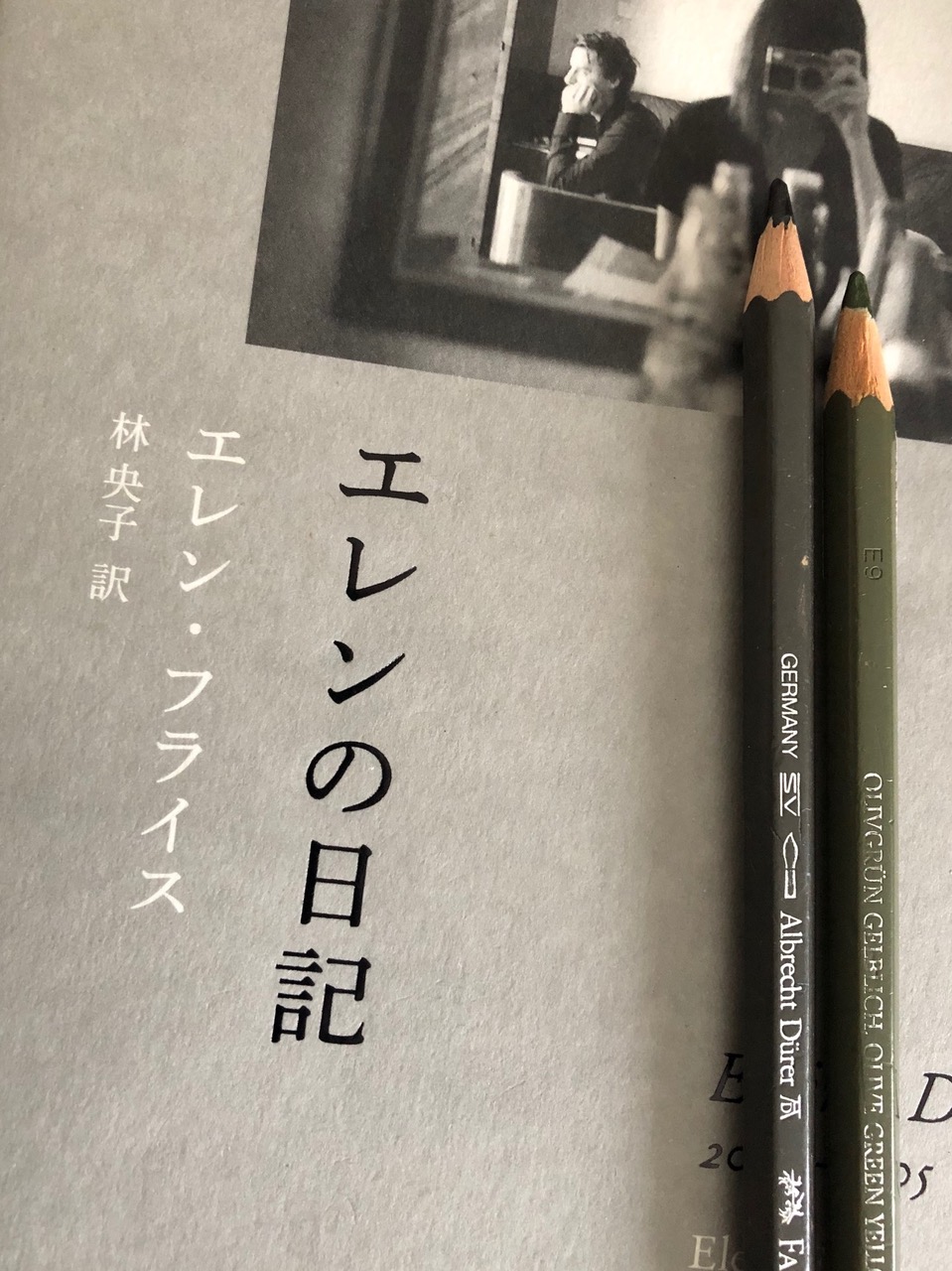懐かしい名前だ、エレン・フライス。『Purple』は、いつも気になるマガジンで、何冊か持っていた。そのあと、『HÉLÈNE』『The Purple Journal』と刊行されたが、エレンについてはしばらく消息を聞かなくなっていた。九十年代後半、若い友人が、パリでエレンの仕事場を訪ねたが会えなかったというようなこともあった。
訳者の林央子は、『花椿』にいた人で、独立して『here and there』という個人雑誌を出し続けて、展覧会のキュレーションなどでもめざましい仕事をしている。『here and there』は送ってもらっていたし、その後も目につくと入手していた。
さて、『エレンの日記』だが、装丁は須山悠里。パリの空をおもわせる沈んだ灰色が美しい、静謐さのあるデザインだ。この仕事は、前に彼が手がけたエレナ・トゥタッチコワの写真集『林檎が木から落ちるとき、音が生まれる』の水脈につながると思う。感動したので、それを伝えたかったが、果たせなかった。それはどうしてだろうと、ずっと気になっている。
最近、ジョルジョ・アガンベンの『書斎の自画像』を読んで、その感想がどうにもコトバにしにくくて、ずっと宙づりになったような居心地の悪さをおぼえていた。いや、コトバにしないことの快楽にふと目覚めてしまったというべきか。アガンベンの他の著作に比べると、あまりにわかりやすくて平明でナイーブなことに戸惑いながら、それこそ、黄昏になってアガンベンと並んで野を歩いているような気分にうっとりしたのだった。
書斎は、本やメモや筆記道具や写真、あらゆるものが生そのものように未整理に混沌として放り出されていて、アガンベンは、それを「非の潜勢力」という。未だ書かれざるものへと至る、あるいはついに至らない潜勢力を描くという試み。それは、エッセイというものが生そのものを掬い上げようとする試みであることに似ているかもしれない。
アガンベンの試みが成功しているのかどうかは、にわかには判断できない。けれど、彼の言い訳めいたコトバは、かって書かれたことのない繊細さと思いがけない強さとで心を揺さぶる。
それは、まるで夕暮れに何かを眺めようとするときにも似ている。光が足らないというわけではないが、だんだんと暗くなるから、見るのを止めることができない。かくして、事物や人物が浮かび上がってくる。見るのを止めることができないということのうちに、つねに留まっていよ。1
思い出すのは、『気狂いピエロ』で、主人公のフェルディナンに扮するジャン=ポール・ベルモンドが、バスタブに浸かりながら読んでいたフォールの浩瀚な『美術史』の中の、べラスケスについての一章だ。
ベラスケスは五十歳を越えると、もはや決して対象を明確な輪郭線で描くことはなかった。彼は空気や黄昏とともに対象のまわりを彷徨い、背景の透明感と影のなかに色調のきらめきを不意にとらえ、この眼には見えないきらめきを核として静かな交響曲を奏でた。彼が世界のなかにとらえるのは、いかなる衝撃、いかなる激発であろうとも、その歩みを露呈させたり中断させたりすることのない密やかで弛みない進歩によって、形態と色調が互いに浸透しあう神秘的な交感以外のなにものでもない。空間が支配している。空間は表面をかすめる大気の波のように、その表面から目に見えて湧き出るものを吸収し、輪郭づけ、形作る、そして芳香のごとくいたるところへと拡散する、ごく軽い塵となって四方に拡がりゆく反響さながらに。2
エレン・フライスの日記は、挿入されたたくさんの写真と同じように、おぼろげで曖昧で、意味のあることだけは言うまいという譲らない姿勢で一貫されている。散漫であることの美点があって、主張したりエゴを押し付けたりすることが一切ない。挿入されたたくさんの写真と同じように、おずおずと控えめに好きなものが羅列されることで成立しているという特異性では、ロラン・バルトの著述とも響きあうだろうか。(エレンが、マルグリット・デュラスの映画への偏愛を告白していることをおぼえておこう。デュラスは、物語を語る際の法則にまったくとらわれていないと評している。さらに、彼女は自分のアイドルは、ソニック・ユースのキム・ゴードンとパティ・スミスだともいう。ボブ・ディランが好きらしいのも、うれしい告白だ。何と言っても、エレンは、圧倒的にセンスがいい女性なのだ。)
エレンは、フランス人が耐えられないのは「常に話しつづけていること。ほんとうは何も言うことがないときでさえ、何かを言おうとする。(中略)私は会話のあいだの沈黙が好きだ。」3といっている。
そのコトバのように、書かれている身辺雑記は、シャイで口下手で、沈黙や余白だらけだ。
ここに登場する友人たちも、エレンにどこか通じるものを持っていて、そのキーワードとして、潜勢力(あるいは非の潜勢力)をあげておきたい。あるいは、中動態、あるいはnegative capability、これまでは負のものとして脇に追いやられていたものを、持ちつづけている人々。スーザン・チャンチオロ、マーク・ボスウィック、アンダース・エドストローム……、共通しているのは、マーケティングというものから遠いところで、「自分自身の欲求からはじめる」少数の人たちだということ。コンセプトからではなく感受性から発想するのでなければ、感情を喚起することはできないと考えているからだ。
ブラジルへの旅の紀行文が、印象にのこった。あの巨匠グラウベル・ホーシャの息子だというエリキ・ホーシャが登場して昂奮した。七十二歳の歌手エルザ・ソアレスのライブを観たという一節にも。
旅のこと、出会った人たちのこと、哲学のこと、政治のこと、カフェのこと、ホテルのこと、墓地のこと、建築のこと、猫のこと、食事のこと、ロシア文学のこと、ファッションのこと、あらゆることがボソボソとした口調で語られる。失意や感情の行き違いや病気や引っ越しや、もちろん恋のことも控えめだけれど。まるで、スーパー8で撮った粒子の粗いフィルムの映像のような思いがけなく生々しい官能性にハッとする。
エレンは、この本は失われた時への旅だという説明をしていて、「郷愁」というコトバを口にする。そして、こんな風にも語っていて、自分を美化しない自己洞察の鋭さと厳しさに驚かされる。自分は個人的にはドラッグのことを考えたりしないが、
「良い食べ物、良いワイン、良いチーズ、そして良い本、良い映画、良い雑誌、さらには良い人間」については、いつも考えている。4
これこそは、表現者にとって取るに足らない潜勢力として、従来あっけなく脇へ追いやられがちなものではなかっただろうか。エレン・フライスは、フランス南西部の街に、十歳になる娘と三匹の猫と一緒に暮らしている。この日記の、最後の〆くくりは、長く心に残る。
私のしていることを例えるなら、産業活動というよりはむしろ手仕事になるだろう。産業化された食べ物より、家庭料理を私は好む。それは、ほかのすべてのことにもあてはまるのだ。5
(さえき・まこと 文筆家)
引用出典
1. ジョルジョ・アガンベン『書斎の自画像』(岡田温司訳、月曜社、2019年)、23頁
2. エリー・フォール『美術史4 近代美術Ⅰ』(谷川渥・水野千依訳、国書刊行会、2007年)、141-142頁
3. エレン・フライス『エレンの日記』(林央子訳、アダチプレス、2020年)、34頁
4. 同、46頁
5. 同、186頁
本テキストは佐伯誠さんのメールマガジン、book review「読んだり、読まなかったり_」からの転載です(2020年4月8日)。
©2020 Makoto Saeki